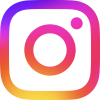ブログ
2025.09.09更新
DX「2025の崖」その後 ~企業を進化(深化)させるための道具「DX」~
DXとはもはや皆様ご存じデジタルトランスフォーメーションの略である。
2018年に経済産業省が「DXレポート」を提唱して久しいこの概念。
日本語に訳せば「デジタル化によって、事業構造・業務プロセスにおいて大幅な改革を行うこと」である。
DXは政府目標Society5・0の一角を担う重要項目だ。
さすがに全く聞いたことがないという方はもう少なかろうと感じるが、足元を見れば、具体的にIT化やデジタル化、IoT、生成AI、5G、WEB3・0などデジタル関係用語が乱立する中、それらとどう違うのか、釈然としないモヤモヤを抱いている方もおられるだろう。
「DXレポート」曰く、DXの「2025の崖」というものを乗り越えなければ日本経済には12兆円規模の機会損失が待っているという。
逆の見方をすれば、12兆円規模のビジネスチャンスがあるということだ。
そうしている間にもついに2025年も半ばを過ぎてしまった。
あの崖はいったいどうなってしまったのだろう。
今回の特集では、DXとはいったい何なのか改めておさらいし、「2025の崖」のその後をまとめてみたい。
DXとは

DXは、将来のデジタル市場において勝ち残るための企業変革である。
現在において“先端”技術といわれるこれらのデジタル技術も、近い将来には、“当たり前”の技術となるだろう。
DXとは、このように、将来主流になると予想されるデジタル市場において、今後も既存の企業が淘汰されず、勝ち残り続けるために、まさに今、多くの企業にとって必須の経営課題として求められている変革なのだ。
経産省によるITサービス市場の中長期的な構造変化予測では、2030年のITサービス市場は半分以上がAI/IoTに移行していくと予想している。
では、そもそもDXとはなんなのか。
DXは、2004年にスウェーデンのストルターマン教授が提唱した「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念で、経産省のDX推進ガイドラインでは
DX=「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」
と定義されている。
DXに関しては多くの論文や報告書等でも解説されているが、中でも、米調査会社IDCは、具体的な専門用語を引用して次のように定義している。
DX=「企業が顧客や市場の破壊的な変化に対応しつつ、組織や文化、従業員の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム※1を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネス・モデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客体験の変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること」。
さらに、企業が生き残るための鍵として、
「DXを実装するための第3のプラットフォーム上のデジタルイノベーションプラットフォーム※2の構築において、開発者とイノベーターのコミュニティを創生し、分散化や特化が進むクラウド2・0※3、あらゆるエンタープライズアプリケーション※4で使用されるパーベイシブAI※5、マイクロサービス※6やイベント駆動型のクラウドファンクションズ(クラウドサーバーを使ったシンプルで一義的な関数)を使ったハイパーアジャイルアプリケーション、大規模で分散した信頼性基盤としてのブロックチェーン、音声やAR/VRなど多様なヒューマンデジタルインターフェースといったITを強力に活かせるかにかかっている。」
としている。
つまり、組織や事業所のDXを進めるためには、より多くのアプリやソフトなどのデジタルサービスと連動できる汎用性の高いクラウドを実装し、そのクラウド上では使用者の業種にマッチした、めちゃめちゃ早くて便利で使いやすく見やすいアプリを取り揃え、もちろんそれらには普及型のAIを実装しており、各々のアプリ間やあらゆる組織内システムと自動的に連動し、更にはそれらのアプリやソフトはカスタマイズや開発が容易であるために、システム開発者を内製化できてしまうような仕組みを事業内容に合わせて作ればいい、もしくは選択すればいいということだ。
ARやVR、動画や音声などを組み込むためには、自ずと組織のIT環境を5Gのような超高速なデータ伝送網へ整備することが必要になってくるだろう。
※1「第3のプラットフォーム」
第3のプラットフォームとは、「モバイル」「ビッグデータ」「クラウド」「ソーシャル」の4つの要素で構成される新しいテクノロジープラットフォームのことで、米調査会社IDCが2013年頃から提唱しているコンセプト。「第3の」ということは、「第1」と「第2」があり、第1のプラットフォームは「メインフレームと端末」、第2のプラットフォームは「クライアント・サーバー」と定義されている。
※2「デジタルイノベーションプラットフォーム」
企業の革新やデジタル技術による新たな価値の創造を行うためのOSやアプリ、ソフトなどを指す。
※3「クラウド2・0」
クラウドは企業のITシステムを大きく変革したが、あまりに急激なクラウド化により、長期的な戦略のない独自サービスが乱立、その結果、相互運用性やガバナンスに欠けるクラウドシステムができてしまった。これが「クラウド1・0」である。この課題を克服した次世代クラウドが「クラウド2・0」であり、高信頼、寡占化、高い処理速度、分散、複数のクラウドを統合的に運用・管理、とてつもなく速いアプリ、誰もが開発者の7要素を統合した概念となっている。
※4「エンタープライズアプリケーション(EA)」
企業内で個別に設置・運用されている業務システムやデータ、プロセス。
※5「パーベイシブAI」
普及型あるいは普遍型AIのこと。AIがビジネス活用フェーズに入り、近い将来、いつでも、どこでも、誰でも、何にでも、パーベイシブAIが適用されるようになるといわれている。
※6「マイクロサービス」
ソフトウェア開発の技法の1つであり、1つのアプリケーションを、ビジネス機能に沿った複数の小さいサービスの疎に結合された集合体として構成するサービス指向アーキテクチャの1種である。
コロナ禍が日本のDXに与えた影響 2025年の崖 その後
ご存じの通り、コロナ禍によって日本のデジタル化の遅れは浮き彫りとなり、多くの企業がその必要性を再認識させられたのではないだろうか。それはDX推進にとっても大きな影響を与え、2020年以降、生活様式の多様化、テレワークやハイブリッドワークといった新しい働き方、新しい生活様式いわゆるNew Normalに対応した商品やサービス、更なる業務効率化の必要性の増加、特に対面機会の減少によって大きなビジネス環境の変化に直面した企業は、DXを推進せざるを得ない状況となった。
国交省の「国土交通白書2021」によると、コロナ禍を契機にデジタル施策に取り組み始めた企業は全体の75・5%を占め、今もなお増加傾向であるという。
一方で日本のDX推進は、他国と比較すると依然として遅れている。特にデータ分析スキルを持つ人材や、ビジネス課題とデータ分析を結び付け施策に繋ぐことができる人材が不足しており、IT人材の獲得がますます困難な状況となる中、中小企業と大手との溝はますます深まろうとしている。
他にも、既存の古いシステムからの脱却(経産省の予測通り、2025年には既存の基幹系システムの約6割が導入から21年以上経過する)、システム変更にかかるコスト、明確なビジョン・目的の欠如、DXのコストが実利に見合うか、経営層が現場のオペレーションを理解していない、現場でデジタル化やDXの必要性が感じられていない、全社的な横断活動に現場が抵抗するなどDX推進に対する課題も同時に浮き彫りになってきており、
DXが進まない場合、2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が発生する可能性があるという指摘は、依然として現実的なリスクとして存在している。
これは新しいデジタル技術を導入できないことによる競争力低下が要因だ。
課題は山積しているものの着実にDXを推進し、成果を出している企業もある。会員の声に掲載している株式会社ミヨシテックはまさにそういった企業のひとつだ。
また経産省は楽天グループの新たな生成AIの基盤モデルの開発を支援する方針を固めた。楽天グループは8月から次世代型の生成AIの大規模言語モデルの開発に着手する方針で、国内で最大級となる7000億規模のパラメータを目指す。
パラメータとは、AIが学習する際に必要な容量などを表す数値で、数が大きいほど高性能な生成AIを創り出すことができる。これまで国内ではコストを抑えた小型のパラメーターで小規模なニーズに特化した生成AIの開発を進めることが多く、楽天も去年15億パラメーターのコンパクトな基盤モデルを公開していた。
7000億規模のインパクトの大きさがうかがえる。果たして、念願の国内初で先進的な生成AIサービスは登場するのだろうか。DXの焦点は間違いなく生成AIへ移り変わろうとしている。
当所では全国商工会議所でもめずらしいIT支援部門である「情報センター」を有し、皆様のDXの一助となれるようAI活用を始め、様々なサービスを展開している。ご興味があれば、ぜひご活用いただきたい。